�@�@�@�@�@�r�����̏ے��I�@�\�ɂ��Ă̈�l�@
�@��s�s��ԂɊւ��镶���l�ފw�E�Љ�S���w�I���_�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�S����
1987�i���a62�j�N9��10�����s�@������w�Љ�E�l�ފw��N���1���l�Ԃ̉Ȋw��
�͂��߂�
�i�P�j�{�e�̖ړI
�{�e�̖ړI�͓s�s��Ԃ̕s�����Ɣr�����̏ے��I�@�\�ɒ��ڂ�,�����l�ފw,�Љ�S���w�̎��_���瓙�֎����ꂪ���Ȕr�����̖����������邱�Ƃł���B
�����l�ފw�̊S�͖��J�Љ�̏��łƂ������ɓI���R���當���Љ�ɓW�J���Ă��Ă���B����������̓s�s��l�ނ��o�����Ă��Ȃ��������Ƒ�����Ȃ�,�s�s�����V���Ȗ��J�n�ł���,�����ɐ��ޖ����ݗ��̒~�ς�p���čl���Ă����Ȃ��,�ɂ߂Ė��͂Ɉ���t�B�[���h�ł���ƌ����悤�B���������S����s�s�߂����ڂɓ���̂��s�s��Ԃ̕s�����Ɣr�����̖��ł������B
�i�Q�j�r�����̖��
�����̗��j�͓����ɔr�����Ƃ̐킢�̗��j�ł�����B�����s�S�͌���Δr�����̏�ɂ���B�]�ˎ���͔r�������̎c�D��,���̌���k��,��Ђ̏ēy��,���C�����X���ߗ��Ă��ė����B��㍂�x�������ɂ͎Y�Ɣr�������}��,8�����^�э��܂ꂽ���̓��ɂ͈���ɎR�������v���X����,�V�h�ԂɘA�Ȃ�قǂ̐��|�Ԃ��E����,���R���Ή�,�Q���̑唭���������p�������B���ǖ��̓��ɂ͖�1�疜�g�������߂��,�����S�~�푈,�Z���N�����Ɩ��͑����Ă���B1)
�i�R�j�����l�ފw�̎��_����
�v����ɂ����������ւ̑Ή���,�r�����̑���ɑ��Ă͏����\�͌���,�V�Z�p�̊J���Ƃ������Z�p�ʂ���̑Ή��Ɍ��肳��Ă����B������l�ފw�̎��_���猩�����ɒ��ڂ����̂�,���������l�ԂɂƂ��Ă��̂��̂Ă�Ƃ�,�r�����Ƃ͉��Ȃ̂�, �Ƃ����Ӗ��̒T���ł���B�{�e�ł͓s�s��Ԃ̕s�����Ɣr�����̊֘A�̌�����ʂ��Ă��������Ӗ��̐��E��T��,���̗����ƐV�����Ή����l���Ă������Ƃ����킯�ł���B
I.�r���Ƃ͉���
�����ł܂�����I�Ȕr�����̏����̎��Ⴉ��,�r���������̈�ʓI�������������Ă݂悤�B����Ŏd��������B���������r�����͏��̏��,���Ȃ킿�����Ⴂ�ʒu�̃N�Y�J�S�Ɉڂ����B�䏊�Ȃ痬���̃R�[�i�[����S�~�o�P�c�Ɉڂ����B�����ƒ���̔r�����͂܂Ƃ߂ă|���ܓ��ɋl�߂��,��U������ɂł��u����Ă���,�������ɐ݂���ꂽ�W�Ϗ��ɉ^���B����ʼnƒ�ł̔r����Ƃ͏I���ł���B
�w�ł͏�q�������̋z�k��G�������z�k�����S�~�o�R�Ɏ̂Ă�B�z�[���̏����H��ɓ����̂Ă�Ƃ����Ƃ肽�Ăĉ����ւ̈ړ������������̂ĕ�������l�����邪, ����͔����̂ĕ��ł���Ƃ����B�������W�������ׂĉ����,���W�ԂɈ����n���B�@�@
���������e�n����̔r�����͎s�������̎��W�ԂŐ��|�H��▄��������ɏW�߂��,�ċp���ĊD�ƋC�̂ɂȂ�,���邢�͒n���ɖ��߂��,�₪�Ă͂��̏オ�������������ɑ������ꂽ�肷��B
�������瓱���o����錴����,��1�Ɂu1�v�ɋ߂Â��邱�Ƃł���B�r�������u�����Â���v�Ƃ͎U��Ƃ��Ă�����̂�1�n�_�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃł���,�����̃`���Ȃ�N�Y�Ȃ��1�́H�H���g�����Ƃ��邱�Ƃł���B���ꂪ����ɏW�Ϗ����琴�|�H��ւƂ܂Ƃ߂���B���Ɏ��I�ω������Ă��ċp,�����Ƃ͐F,�`,�傫��,�ގ�,�L�C�������l�Ȕr�������قƂ�Njώ�,���F,���L�C�̕����ւƕω������邱�Ƃł���B
��2�ɂ�,��ԏ���I�������u�ĂĈړ����邱��,�����Ă��ꂪ�Љ�I�P�ʂƘA�������i�K��ōs�Ȃ��邱��,�����Ă��̈ړ�����������邱�Ƃł���B���Ȃ킿���̓N�Y�J�S�܂�,�ƒ��P�ʂƂ��ďW�Ϗ��܂�,����P�ʂɐ��|�H��܂�, �Ƃ������ړ��ł���, �������ړ����ɂ킴�킴���������,���H��ɂ܂œ����̂Ă�,�H��ɓ����̂Ă���킴�킴���Ƃ��Ƃ������s�ׂł���B
��3�ɂ͂��������r���͓����Ɋ�Â��čs�Ȃ���ׂ��Ƃ����B�܂�N�Y�J�S,���|�H��Ƃ������{�݂̐ݒ�,���O�������̋K���Ƃ���,����n�[�h�E�G�A,�\�t�g�E�G�A�̗��ʂ���r���̎d������������Ă���Ƃ����_�ł���B
II�D�Ȃ��r�t���͔r�������̂�
�i�P�j����,�s�����Ɣr��
�ȏ�̌������ӂ܂���,���ɔr�����͉��̔r�������̂���,�܂��͐���,�s�����Ƃ�������ʓI�ɍl������_���猟�����Ă������ƂƂ���B
����,�s�����Ɣr���̊W���l���邽�߂ɔr���̗��j���l���Ă݂��,�]�ˎ���̓��{�̒���,�����l�̖ڂɂ͑�ωq���I�Ŕ��������������Ƃ������L�^�Ɏc����Ă���B2)�����������[���b�p�̓s�s�ł͐l�X�̓g�C���̂Ȃ��Z��牘����H��ɂԂ��܂�,�X�H�𑖂���̌Q�ꂪ�����H���U�炷�Ƃ�����Ԃł���,�����̋N�������͉����̎R�̒��ɕ��s�X�y�[�X���m�ۂ��邽�߂������Ƃ��������炠����ł���B3)�����������͓����̐�����,�s�����̑���ł���,�����l�͐��Ƃ�����̕s���Ȗq�~���S�ł���,���͋��L�قǑN�x��v������Ȃ�, �Ƃ���������Ƃ��֘A����Ƃ����w�E������B3)�܂������̓s�s�͎s�ǂɈ͂܂�Ă������ߓ������ߖ�����,���̏������,�_���������������܂ꂽ���߂ɉq����Ԃ����������Ƃ������Ă���B������ɂ���y�X�g�̑嗬�s�œs�s�l����1/3����1/2������ꂽ14���I�ɂȂ��Ă悤�₭�s�s�̉q���ւ̊S�����܂����̂ł���B3)
�������䍑�̏ꍇ��,�s�s�̐������͕K�������q���ւ̊S�̍����̌��ʂƂ͌����Ȃ��̂ł���B�]�ˎ��㕳�A�͒n��,�Ǝ�̏��L���ł���,�_�Ƃɔ엿�Ƃ��Ĕ���n���������Ƃ����B�R���ł͉���𑝂₷���߂Ɋ��ŋq�𔑂߂��ƌ����,�吳����ɂȂ��Ă����A���Ǝ�̂��̂�,�؉Ɛl�̂��̂����ٔ��ő���ꂽ�Ⴊ����قǂł���B4)���Ȃ킿�����ł̓x���T�C���ɂ��I�y�����ɂ��g�C�����Ȃ��������Ƃ͗L������,���{�Ńg�C������������g���,�����V�X�e�����������Ă����̂�,���͔엿�m�ۂ̂��߂��Ƃ�����������̂ł���B5)�������ĉq���̂��߂ɔr������Ƃ������z�͕��Ր���ے肳���̂ł���B
�i�Q�j���p�I�@�\�Ɣr��
�ł͎��p�I�@�\�̑r�����r�t�𑣂��̂��낤��?���B�̓C���N�̐ꂽ�{�[���y��,�ÐV��,��̃N�Y����r������B�����͏���,�ǂ�,�H�ׂ�Ƃ������p�I�@�\���ʂ����Ȃ��Ȃ�������ł���B���������p�I�@�\�r���ɂ�������炸,����肾����,�D�݂ɍ���Ȃ�����,�����ċC���]���̂��߂ɔr������Ƃ������������B
�i�R�j�|��
���ɓ������ꂽ�r����Ƃ̑�\��ł���|���͉��̂��߂ɍs�Ȃ���̂�����������B�����̗�ł�,�n�ʂɂ��Č��̑������n���~���E�Ƃ��������ȍb���̈���,�����Ȃǂ𓊂����܂��Ƃ����ɔr������B�C��ɑ������M�{�V���V�͑��̒���₦���V�N�ȊC���������悤�ɂ���B�Ƃ��낪���������ł����Z�̉��ނ͑|�������Ȃ��Ƃ����B
�l�Ԃ̗�ł�, �s�O�~�[�͐��T�Ԃ���1�`2�����ŏW�����ƈړ����Ă��܂���,���̊Ԃ͂�����Ƒ|��������B�}���}���O�Ƃ������̑傫�ȋ��~�`�̗t��g�݂��킹�����������悤�ȏZ���̏��ɓ����t��~����,�������������ꂽ�t���W���̎��͂Ɏ̂�,�X����V�����t���Ƃ��Ă��ĕ�[����B6)
�ȏ��v����ɔ��Z�Ȃ�|�����Ȃ��̂ɑ�,�����Ƃ����̋�Ԃɒ�Z����ꍇ�ɑ|�����s�Ȃ���Ƃ������ƂɂȂ�B����͒�Z����Ύ��Ԃ̌o�߂Ƌ��ɔr�����ׂ����̂��������邩��Ƃ��l�����邪,�����r�����ׂ����̂��Ȃ��Ƃ��|�����s�Ȃ���������B
�܂��w�A�[�C���f�B�A���̏ꍇ,�Z���ɂ͓���炵�����̂͂قƂ�ǂȂ�,�c�蕨�̓\�������H�ׂĂ��܂�,�r�����͂قƂ�Ǐo�Ȃ���,���̃g�h���̍}���������ւ�,�V�������Ƃ̍��肪�Y���Ă���B6)
���ɑT�@�ɂ�����|���ł���B�ߑ��͑|���̌܌����Ƃ��āu���S����,���l����,���V���삷,�[��̋Ƃ�A��,���I�̌�܂��ɓV��ɐ����ׂ���v�ƌ����Ă��邪,�T�@�ł́u��|��,��Ōo�v�ƌ������,�C�s�͑|���Ɏn�܂�|���ɏI���B���ꂾ���O��I�ɑ|������Δr����������͂����Ȃ���,�T�@�ł͑|���͎��͏C�s���̂��̂Ƃ���,�����āH���Ƃ����|���ɓO���Č����J�����m�̘b�����`�����Ă���B7)
�������E�̊w�Z�Ő��k�ɑ|���������鍑�͕������ɑ���,����1�ł���䍑�ł��w�Z�|�������H�Ƌ��ɋ���̈�Ƃ��Ĉ����Ă��邪,�T�@�ɂ����đ|���͖{���̋@�\�Ƃ͕ʂ�,�C�s,�J��̂��߂̎�i�Ƃ���,�������I�@�\��^�����,���̂��߂ɓ������K�v�Ƃ���Ă���Ƃ����킯�ł���B
����ɖ{���Ƃ͈قȂ����@�\�����������Ƃ��Ė��c���j�̐�������B���c�͍����̂悤�ɐo�������Ȃ����̂͏����̊ԂɖؖȂ����y����悤�ɂȂ��Ă��炾�Ƃ�,�ؖȂ�т����y��������_�����̊Ԃł͑|���͂��܂�s�Ȃ��Ȃ������Ƃ��Ȃ����,�������}����12��13��,���[��7��11���ɑ�|�������邱�Ƃ��w�E��,�|���͐������,���Ԃ��u�P�v����u�n���v�芷���邽�߂ɍs�Ȃ���Ǝw�E���Ă���B8)
III.�s�s��Ԃ̕s����
�ȏ�̌������猾���邱�Ƃ�,�r���͂��̂̋@�\�̗L��,����,�s���Ƃ������_���炾���s�Ȃ���킯�ł͂Ȃ�,�{���̋@�\�Ƃ͕ʂ�,����Α�2�̋@�\�Ƃ������ׂ��@�\��]�����꓾��Ƃ������Ƃł���B���ɂ���q�̈�ʓI�����̂���,�\�Ȍ���ul�ɋ߂Â���,�������u�Ă�, �Ƃ������_��,�s�v��,���邢�͉ߏ�ȏ����팸��,���̒��̏���̏ȗ͉���}��@�\���ʂ����ׂƂ��l�����邪,�{�e�ł͓s�s�̖����l���闧�ꂩ��,�s�s�̕��������1�̖��ł���s�s��Ԃ̕s�����Ɣr�����̑�2�̋@�\�Ƃ̊֘A, �Ƃ������_����l���Ă݂悤�Ƃ����̂ł���B
�i�P�j�s�s��Ԃ̕s����
�ĎR�r���͓s�s�����̃n�������ۂ��w�E���Ă���B9)�����̓s�s���������Ԃ̑��ʂ��猩���,�֗����Nj��̎Y���ł���n�E�X���G�A�R���͋G�ߊ���,�^��p�b�N�̂����̓n���̎��Ƃ��Ă̐�����D�����B�N���Ղ�̂悤�Ȕɉ؊X�͍Ղ�̊�т�D���B�߂��݂̎������邩�炱����т̎����P���̂ł���,���������Z�W,�N���̏��������Ԃ�,�܂��ɔ�l�ԓI��,�s�����������Ԃƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
����͋�Ԃ̏ꍇ�����l�ł���B��ʖԂ̔��B�͉�����,�߂����̋�ʂ����ł���,����ȋ�ԂɎ�X�G���Ȑl����̂��W������B�ǂ������������ɉ�,���������藧�Ă��,���邭�Ɩ������B�ÈłŋC���̈��������Ȃ�,�S�̑������߂Ȃ�,�����ʂ�̓s�s����,�s�s�W�����O���ƂȂ��Ă���̂ł���B���������s�s��Ԃ͂܂��ɂƂ炦�ǂ���̂Ȃ�,�̂���ڂ���,�s����������l�ԓI��ԂƂ������ƂɂȂ�B
�i�Q�j�s�s��Ԃւ̉��l�ς̓��e
�ł͋t�ɂ̂���ڂ��łȂ��s�s��ԂƂ͂ǂ�������Ԃł��낤���B
�������ɂ��]�˂̒��͏�𒆐S�Ɂu�́v�̎��`�ɕ���,���{,��Ɛl,���l,�O�l�̏��ɏZ��n���ݒ肳�ꂽ�Ƃ����B10)�Љ�I�����Ƃ��̋敪�����̂܂ܕ����I�����ɒu���������Ă�����,�x�z�҂ɂƂ��Ă͂܂��Ɏ���̉��l�ς����̂܂ܓ��e���ꂽ��Ԃł���,����͂܂��Z���ɂƂ��Ă���ς͂�����Ƃ��ނ��Ƃ̂ł���,�����ʂ���̓s�s��Ԃł������͂��ł���B����ɂ����Ŕr�����Ƃ̊֘A�Œ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�,�Y��[�Α���∫�ꏊ�̐ݒ�ł���B���Ȃ킿�܊X���̓����ɂ͊e�X�n�����z����,�S��ɂ͏�슰�i�����u���ꂽ��,�����X��������ɉ�������Z�ɂ͏��ˌ��Y��ƉΑ���,�����Đ�Z�h�ɂ͗V�f���ݒ肳�ꂽ�B���C��������Εi��ɗV�f,����ɗ�P�X���Y��ł���B�܂����g�������{���̓s�S���ɔ�����,������ӂ̎ŋ����������ꏊ�Ƃ��ĐɈړ�������ꂽ�̂ł���B���Ȃ킿�₩��,���邢�͋߂Â��������悤�ȏ��s�S���Ƌ���,�������u�Ă����ɂ͉��ꂽ�ꏊ�∫�ꏊ��,�X�������̐l�X�̖ڂɂ���ł����݂���������悤�Ȓn�_�ɐݒ肳��Ă����̂ł���B�������Đݒ肳�ꂽ�n�[�h�E�G�A�Ƃ��Ă̓s�s��Ԃ�,�����ʂ�N�̖ڂɂ��͂�����ƌ�����,�Ӗ��I�ɋN���ɕx��,�̂���ڂ��ł͂Ȃ���Ԃł������ƌ����悤�B�����Ă����Ń}�C�i�X�̈Ӗ������^�����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���鎀�����,�u�Ă��邱�Ƃɂ����,�܂��܂��t�����̒��S����s�S�Ƃ��ċP������ׂ�,�ϋɓI�ɗ��p����Ă��邱�Ƃɒ��ڂ������̂ł���B
�W.��Ԃ̉����Ɣr�����̋@�\
��̎��Ⴉ��͌Y�ꓙ�u�������ׂ����̂��s�s��Ԃ���������@�\��]������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ��ł��邪, �������Y�ꓙ�̐ݒ�͂���Γs�s��Ԃ̃n�[�h�E�G�A�̑��ʂł���,���ۂɂ͓ƍٓI�x�z�҂̑��݂��Ȃ�����̓s�s��W���̋�Ԃł�,�����I�����œ��e���c�߂��Ă��܂����Ƃ�,��U�ݒ肳��Ă��ϓ��𔗂��邱�Ƃ�����͂��ł���B����ɂ܂��n�[�h�E�G�A�����ł͂Ȃ�,�����ɂ͂��̋�ԓ��̗l�X�Ȃ��̂�l�̈ړ��̎d���̖��,���Ȃ킿�\�t�g�E�G�A�̑��ʂ����݂���͂��ł���B�Α����ݒ肵�Ă������Ɏ��̂��ʂ̏ꏊ�ɔr�����ꂽ�̂ł͋@�\���ʂ������Ȃ��킯�ł���B�����Ŕr�����̓������傫�ȈӖ������͂��ł���,�ȉ��ł͐V�����������S�Ó쒬���ʂ������,�r�����̈ړ��̓�����,��Ԃ̉����̊֘A���l���Ă������ƂƂ���B
�}1 �Z����Ԃ�1��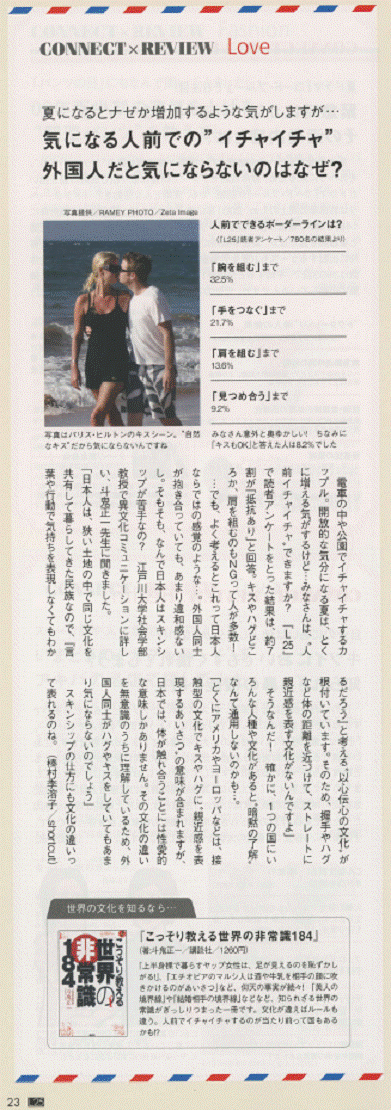
�i�P�j���ʂ̎���
1)�Z�����,������Ԃ̐ݒ�
���ʂ�37����,�l��139�l�B�O��鋫�ƌ���ꂽ�H�R�������H�R�X���ɉ������ߑa�̍���̃����ł���B�]�܂����Z����Ԃ̓J�~, �V���Ƃ������ʂ����W����,��ԃJ�~�̃I�N�Ƀg�V�����̐Q���ł���,��c�`���̉ƕ�u���I�I�x�A��݂���B�����ɂ̓I�I�x�A�ƕ��s�����I�I�x�A�̃V���ƕ\�������ʒu�ɂ�,���d��_�I������,��ȋq��ڑ҂�,�V����s�Ȃ��U�V�L������B���̃V���Ƀ`���m�},�����Ă��Ƃ��Ƃ͓y�Ԃ������j��,�J�b�e�ƕ���,�Q���J���̓j���ƕ��s���Ă��邪�ł��V���Ƃ����B�r���ׂ̈̎{�݂ł�,�Q���J�����Ɏd����Ȃ����C�ƕ֏����݂���ꂽ�B���̗��͊O�ɒʂ�,����ɊO���ɖx��ꂽ����1�̗���,���C���ƕ��A�������Ă˂���,�엿�Ƃ����B�S�~���̓J�b�e�ƃQ���J����,�`���g��,ⴂ͎����p�̓j��,���O�p�̓Q���J���ɂ���B�g������������Ǝ����p�����O�p�ɓ]�p����,���Ȃ킿�J�~����V���w�ړ����邱�Ƃ͂����Ă��t�͂Ȃ��B�܂��V���ɃU�V�L�̂���Z���̓T�J�T���V�L�Ƃ����Ɖ^���X���Ƃ����B���H�V�ݓ��ʼn��z����ꍇ���{���͑S�ʓI�ɔ��]�p�^���ɍ��ς���ׂ��Ƃ����B
���Ƀ�����Ԃł���B���Ƃ͖{�Ƃ��J�~�ɏo���Ă͂����Ȃ��Ƃ���邽��,�Â��{�Ƃ��Ȃ킿�Ɗi�̍����ƂقǃJ�~��,�V����,�Ɗi�̒Ⴂ��,����l���Ɠ��قǃV���ɕ��Ԃ��ƂɂȂ�B�}2��NN����������{��,TS��T���S�����̑�{��,TK�����̕���,TA�͕���l���Ƃł���,�ł��Â��ƁX�͂��̓����ʂ�ɐݒ肳��Ă���B��n�̓V���̃����U�J�C�t�߂�,���͂ɉΑ���,���J���̓������ꂽ�������Ă��邪,���ʂł͋ߔN�I�L�m�n���Ɉړ]�����B
�}2 ����
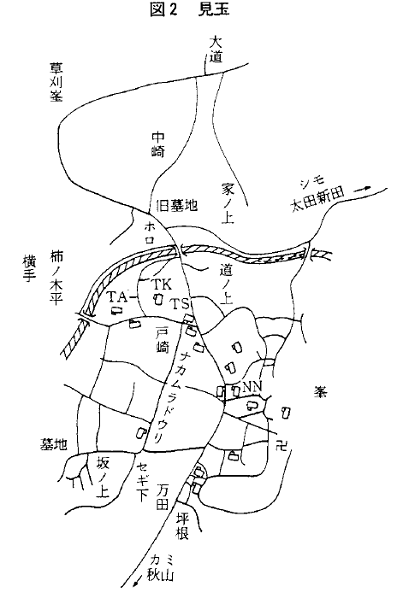
�}�R�@
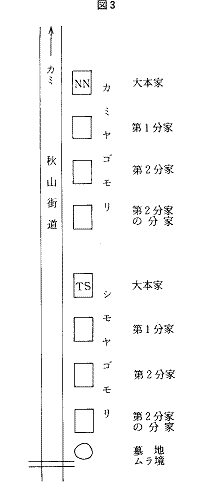
�]�ˎ���ȑO�ɂ̓N�`�x���V�ɐԂ�V���̂Ă��j�J�b�R�o���V�������U�J�C���H�R�X��������ɃV���w���������ɂ���,����ɉ��������ɂ̓E�}�X�e�o���������B
2)���e�̌���
���̂悤�ɐݒ�̍��W���Ƃ����J�~, �V���͎��͒P�Ȃ���ʂł͂Ȃ��B�J�~�͐�D�{��,�N����,�Â����X����u���Ƃ������Ⴉ��݂���悤�ɌÂ�,�����Ēj�Ƃ����D�ʐ���, �V���͎q��,����,�N����,�V����,���Ƃ�����ʐ����ے��I�Ɏ������ʂł�����B�����Ă��̎��Ԍ����ɂ���_�W���^�̗D��W�������ʂ̐l�X�̎Љ�\���ɑ����{�I���l�ςȂ̂ł���B���Ȃ킿���ʂɂ�N��T��2�僄�S����������,NN���J�~���S�����ƌĂ��N��,TS���V�����S�����ƌĂ��T�̑�{�Ƃł��邪,NN�̓N�T���P�ł���,TS�̖{�ƂƂ������,�Ɗi����ԍ����B����Ɋe���S�����͑�{�Ƃ̕��Ƃ��炳��ɕ��Ƃ����ƁX���E�`���S�����ƌĂ�鉺�ʏW�c���`���B��{�Ƃ͑�n��ł���,�����ɂ̓��S�������W������B�V�玞�����W��,��{�Ƃ̎w���̉��ɓ������B��{�Ƃ̓c�A�����ɂ͑S���Ƃ��삯�t��,�؋�,���k,�����J�������܂��E�`���S����,����ŕs���̏ꍇ���S�����S�̂ŋ��͂��s�Ȃ���B�����S�̂����͂���̂͊e���S�����̗͂����ꍇ�ł���B�����Ɍ����錴���͍L�t���̗t���`�̌����ł���,�}�����ꂵ�Ă������̂��i�K�I�ɓ�������,���X���x���������Č��ǂ�1�_�ɏW������Ƃ���1�����u���^�ł���B���Ɋe�Z�����ł���B�o��,����,������ʼn��������l�X�ɂ�,���Ԍ����ɂ��Ԃ�V,�q��,�N,�ˎ�,�ˎ�̌Z��ƒi�K�I�ɏ�����,�e�X���̖���������,�����B�����čŌ�͕���l�ȊO�͍ł��D�ʂ̃g�V�����ƂȂ�̂ł���B�����ł����Ԍ����ɂ���A�����ƒi�K�I�㏸,�����čŏI�I��1�_���߂���1�����I�����ł���B
�������Č��ʂɂ����Ă͈�т��ėt���^��1�����I�������т���, ������ێ����邱�Ƃ�����,�o��,�V�瓙������ǖʂň����ۏ��邱�ƂɂȂ������̂ł���,�Z��,������Ԃ���q�̌����ʂ�ݒ肳���Ȃ��,�}3�̂悤��,�܂��ɍ]�˓��l�ɐl�X�̉��l�ς����̂܂ܓ��e���ꂽ��Ԃ����������, �Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
3)���e�����ƕ����I��Ԃ̂���
�����Ŏ���,�����Ǝ��ۂ��r���Ă݂��,�K�����������ʂ�ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B�{���Ƃ̔z�u��NN,TS,TK,TA�ł͌����ʂ肾��,���̌�̕��Ƃ͕K�������V���ɏo�Ă��Ȃ��B��n�͈ړ]���Ă���B�Z����Ԃł̓I�I�x������ԃJ�~�Ƃ����Ă������ɂ̓U�V�L�Ɠ����W�ł���B��N�̃`���E�������z�̓V�������ł͂Ȃ��B�o������l�����,�I�I�x���ȊO�͒��ڊO�Əo����ł��邩��U�V�L���K�������I�N�ł͂Ȃ���,�I�I�x�����璼�ڏo����̂��U�V�L�ł͂Ȃ�,�`���m�}�ł���B�܂��`���m�}�ƃj���̓V���͋�肪�Ȃ�,�d��˂��Ȃ������B�܂������ߔN�ɂ͗{���̂��߂ɃJ�b�e�O�`��݂����Ƃ����������B
4)����̕
�ȏ�̌����ɂ���,�{���Ȃ牿�l�ς����̂܂ܓ��e������Ԃ��ł���͂���,�����ɂ͘c�߂��Ă��܂��Ƃ����킯��,����Ȃ�\�t�g�E�G�A�ɂ���ăn�[�h�E�G�A������̂ł͂Ȃ���,�����Ĕr���������̍ێg�p�����̂ł͂Ȃ���, �Ƃ����̂��M�҂̗\�z�ł������B
�@���ǂ������ł܂�������Ԃ�Ƃ����������ꂽ�r���ł��钹�ǂ����Ƃ肠����B�����1��14���������̖�,�q���B�����q��ł�,���ǂ��̉̂��̂��ĊQ����r������s������,�o�H��TS�O����o������NN�̑O���o�Ĉ�U�����̃J�~�֍s��,�������璹���V���̃������܂ŏH�R�X��������ǂ��Ă����̂ł���B�̂̓V���̃g�i���������c�V�c�Ƒ������Ƃ����B���̐�͒��ǂ��̂ɂ���悤�ɃV���փV���w�ƒǂ��Ă���,�Ō�͍��n�ɔr������Ƃ������̂ł���B����ɂ��Ύ}����ɂ���TS����NN���o�ăJ�~�Ɍ�����,����ɓ��̃�����Ԃ̒��̈�{���������V���w�������Ĕr��������,N��T���ꎟ���I�ɃJ�~�V���̏����W�̒��ɂ��邱��, �V���̓J�~�̊Q�����r�������ׂ������ł��邱�Ƃ�,�̂Ɣ��q�Ƃ�����ϖڗ����o�ŏے��I�Ɏ������킯�ł���B
�A���̂̔r���̓z���h�E���ƌĂ�����̌o�H��p���˂Ȃ�Ȃ��B�z���h�E���̐ݒ�͐}4�Ɏ������悤�Ɋe�Z����1�{���Ō���,�����ĕ��������Ȃ��B�}���ɂȂ�ꍇ���K�����,���ʂ̏�������B����̎}����ɂ���Z���̏ꍇ,�܂����Ɛ�p�̃z���h�E���ɏo�Ă���i�K�I�ɏ�̃��x���̃z���h�E�����o�ďH�R�X���ɏo�邱�ƂɂȂ�B�ߓ��������Ă����p���Ȃ����A�V�����ł��Ă��ύX����Ȃ��B�����Ă��̃z���h�E���������̓������,�J�~, �V���̍��W���Ƃ���Ă���̂ł���B
�}�S
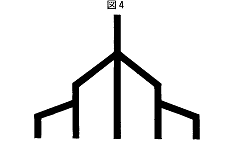
���̎���ɉ��Ă�,����Ƃ������ڂ𗁂т�@��Ƀz���h�E�����̃J�~����V�����r�������ׂ������ł��邱�Ƃ��������Ƃ����킯�ł���B
�B���O���ǂ��@�Z����ԓ��œ������ꂽ�r���̗�Ƃ��ă��O���ǂ�������B���̍s���ł�,�Â��ŏ����������ă��O�������ɊO�֔r�����邪,�����͂܂��I�I�x��,���ɃU�V�L,�`���m�},�J�b�e,�j��,�����Č��ւ���O�ւƌ��߂��Ă���B
�C�|��,�R�G�j���E�@����̑|���͒�1��ł��|��,�̊Ԃ����G�Ђ�������B�n�^�L�͂��܂�g��Ȃ��B���̏ꍇ�K���^����ɃI�I�x����|���o��,���Ɉ�U�U�V�L�ɉ��,���ꂩ��I�I�x���ƃU�V�L�̔r�������܂Ƃ߂ă`���m�}��|��,�J�b�e,�j��,�����Č��ւ���|���o����,�}1�Ɏ������悤�Ɍ��ւ������ɍs���E��ɂ���R�G�j���E�ɐςށB�䏊�̐��S�~�͋��n�̃G�T�Ƃ��Č��ւ̃E�}���ɉ^��,���n�̃����N�Y,���A�͂܂��Ă�͂�R�G�j���E�ɉ^�ԁB���̑������܂┯�̖т܂�,�قƂ�ǂ��ׂĂ̔r�������R�G�j���E�ɉ^��,���s�����Ĕ엿�ƂȂ�̂ł���B�w�\�̏�,��Y�����ւɂ���E�}���ɖ��߂��B
�D�����@���҂͎�҂ł����Ă���U�g�V�����̕����ł���I�I�x���Ɉړ�����, �V���}�N���ɐQ������B�Ւd��J���̓���̓Q���J������^�э��܂��B���J���Ɏg�p�����^�H���͉Α����ɏċp����B�i�x�͓����g�킸,�z�c��49���Ԍ����łق��B�m�̓U�V�L���璼�ڏo���肷�邪,�Q��҂͌��ւ���o���肷��B�H�H�x���œ����㎀�҂̓U�V�L�ɉ^��,���V�I���Ƌ��Ƀ`���m�},�j����ʂ��ăQ���J������^�яo�����B�o����͌L�Ŏ��̂�u�����ꏊ���k��,�V�I�~�Y�o���C�Ə̂��Ē��q�ɉ��������,���҂̕�������I�H�x��,�U�V�L,�`���m�},�j��,�Q���J���̏��ɎT���Ďc����O�Ɏ̂Ă�B�@
�ȏ�̏Z����ԓ��̗�ł�,�K������1�����I�ɐݒ肳��Ă��Ȃ��Z����ԓ��̊e������,�V��Ƃ����l�X�ɒ��������@���,�ɂ߂�1�����I�Ȕr�����̈ړ��ɂ���Ēi�K�t�����,�����t�����Ă���Ƃ����삯�ł���B
5)�܂Ƃ�
�������,�Z����Ԃ̑o�����猾���邱�Ƃ�r���̈�ʓI�����ƑΏƂ��Ă݂��,�܂��u�P�v�ɋ߂Â���,�i�K�I�ɋ������u�Ă�,�������������,�����ē���������, �Ƃ���4�̓_�Ƃ����S�Ɉ�v���Ă��邱�Ƃ��삩��B�����������Œ��ڂ����̂�,�u1�v�ɋ߂Â��铝����2�����̋�Ԃ�i�K�I��,����̏�����1�{��,1�_�Ɏ��q�����錴���ōs�Ȃ��Ă��邱��,���̒i�K�⏇�����{���Ƃ�ƒ���ł̊e�����̒n�ʂ̋敪��D��W�ƈ�v���Ă��邱��,�����Ă����ĉ��ꂽ���̂��l�X���g�̖ڂɖڗ��悤�Ȉʒu,�@��I������Ă��邱�Ƃł���B
V. �@���_
�i�P�j
��K�͉����������z�ȓ����ɔ䂵�Č��ʂ��傫���Ȃ����Ƃ��w�E����,11)�������̊������l�X�̉����ւ̊S��ቺ����,����,�����ʂ������Ă��܂����Ƃ����̌����ł���Ƃ����Ă��邪,�r�����������͍s���ɂ����W�T�[�r�X�������ł���Ƃ����ᔻ������B����͑�1�Ɏ��W�T�[�r�X�����T�C�N����f�����Ă��܂�������ł���Ƃ����B���Ƃ��ƍs�����ƒ�̔r������ӔC�������Ď��W����ȂǂƂ����T�[�r�X�͂قƂ�ǂȂ������B�]�˂̒��̂悤�ɑg�D�I�ɍs���Ă����̂͂�����O�I�ł���B12)���قlj����Ȃ��ߋ��ɂ����Ĕr�����͔엿,�R���Ƃ���,�앨�Ƃ������`�Ŗ߂��Ă����B�s�s�̕��A���_�ƂɈ�������,�ӗ�̖���߂��Ă����B�Ƃ��낪���W�T�[�r�X���n�܂�Ǝ�y����,�����ŋ����Ƃ���Ȃ�o���˂Α��Ǝ��W�ɏo���Ă��܂�, �Ƃ�����ł���B��2�ɂ͔r������l�X�̖ڂ��牓����,�ߏ�Ȑ����u���Ƒ�������,����,�s�����ɑ�ϊv�������N����,����ɂ���Ė�肪�܂��܂��[���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����w�E�ł���B�����ł̓I�����s�b�N���T����1961�N�Ɏ艟�����W�Ԃ�,64�N�ɂ͖ؐ��S�~�����p���������B1)�ƒ�ł������͎���,�����ł͔����|���܂ɋl��,�|���y�[���ɓ������Ă��܂���,��͖ڂɐG��邱�Ƃ�,�L�C���Ȃ�,�≏�ɔ������h�����ꂽ���W�Ԃ������������f�B�[�Ƌ��ɂǂ��������։^�ы����Ă����B�_�X�g�V���[�g������ΏW�Ϗ��܂ʼn^�ԕK�v���Ȃ��B�f�B�X�|�[�U�[�Ȃ琅�Ƌ��ɗ������邾���ł���B����ƋH�Ɏ����̖ڂ��ɐG���悤�Ȃ��Ƃ������,��ϕs���Ȃ��̂ɐG��Ă��܂����傣�Ɋ����邵,����܂ŕs���Ɗ����Ȃ��������̂܂ŕs���Ɋ������Ă��܂��B����ɔ��Ԃ�������̂��ߏ�v�Ȑ����u���ł���B�y�X�g�Ől���������������[���b�p�̗�������܂ł��Ȃ�,�䍑�ł��`���a�̋��|���������ꂽ�̂͂��قlj����̂ł͂Ȃ��B���߂ē��{�l�̎�ō��ꂽ�_�c���������R������ł������傣��,���������߂�v�z���`���a�Ǖ��ɉʂ��������т͑傫���B�����������ɍs���������ߑ�q���v�z�̓v���X�`�b�N,���,�_��ݏo��,�d��Ȗ����Ђ����������B���炩�ȕ\��,���l�ȐF��,���ꂪ����������v���X�`�b�N�B�����ڂ̓G�ɔ���������������CM�B���R����,�l�H���u���̎Y���ł���_��B�����͂��ꎩ�̂��������ł���Ƌ���,�܂��܂��l�X�̐����u��������,�r�������܂��܂��s���Ɋ��������邱�ƂɂȂ�B
�������Ĕr�����͉��̖��ɂ�������,�s���ɂ܂�Ȃ����̂ƂȂ�,�l�X�Ɍ�������,�܂��܂���ʂɔr������邱�ƂɂȂ�B�������͔r�����̈ړ����x���������邽�ߎ��R�̎����p�͒D����B���Ǎs���͂܂��܂����W�T�[�r�X����ɗ͂����,���z���J��Ԃ��Ƃ����삯�ł���B
�i�Q�j
�ł͂����������z��f����Ζ��͉����Ɍ������̂ł͂Ȃ����B���Ȃ킿�r�����������Ė��p�̎ז����ł͂Ȃ�,�d�v�ȋ@�\���ʂ������̂Ƃ��ė��p�����Ȃ��,���ꂪ��ɐl�X�̖ڂɓ����Ă���Ȃ��,��������ω�����,���T�C�N������,�ړ����x��ቺ����,�r�������̂����������邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯�ł���B�����ŕM�҂����ڂ����̂�,�l�X�ɂ�鉿�l�ς̕����I��Ԃւ̓��e��,�����ɑ���@�\�Ƃ����_�ł������B
���\�|�^�~�A�ł͓s�s��Ղ�3�`4000�N�Ԕr������ςݏグ���n�w�̒��ɂ���Ƃ����B����͍^����ł���Ƃ����������邪,��Y�o�͓V��,��n,�n�ꂩ�琬�鐢�E�ς������\�|�^�~�A�l��,�s�s��r���ɂ���ď���֍��߂邱�Ƃ͓V�ւ̎u������,�����r���ǂ�n���ɍ�������,����,�r�����������֔r�����邱�Ƃ͒n���̐_�ɓ͂���C�q�ׂł������Ƃ����B3)���Ȃ킿�r������,�㉺�����Ɉړ������邱�Ƃ���ēV��,��n,�n��Ɛ��������ɘA�Ȃ�F���̃V�X�e���ɎQ����,�Đ��Y���Ă������Ƃ����̂ł���B���������ꍇ�̔r�����͂܂��ɕ����I��Ԃւ̐l�X���g�̉��l�ς̓��e�Ƃ����d�v�ȏے��I�@�\��]������Ă���ƌ�����͂��ł���B
�����Ŏ��Ɍ��ʂ̎�����ēx�������Ă݂��,�ݒ肪�����ʂ�Ȃ�ΐl�X�̉��l�ς̓��e���ƂȂ�͂��̃������,�Z����Ԃ�,�����ɂ͂��̒ʂ�ɐݒ肳��Ă��Ȃ������B�܂����̒ʂ�ɐݒ肳�ꂽ�Ƃ��Ă�,�����ɕ�n�Ɏ��̂��l�X�̖ڂ̑O�Ŕr������Ă����̂łȂ��Ȃ��,�ݒ�̈Ӗ��͂Ȃ����ƂɂȂ�B�Ȃ���̃������,�Z����Ԃ̏���ړ����čs���r�����̈ړ������邱�Ƃɂ����,�܂�\�t�g�E�G�A�̑��ʂ���,���e��������,���e�̘c�݂����邱�Ƃ��ł���͂��ł���,�܂����̕K�v������͂��Ȃ̂ł���B
�����œ����̓��e�ł���B��Ɍ��ʂ̔r���̌����͈�ʓI�r���̌����ƈ�v����Əq�ׂ��B�������ׂ����l���Ă�����,���ʂ̓���J�͕K��������ʓI������q���ςł͐����ł��Ȃ��_�������̂ł���B�܂��������u�Ă�ۂ̓���̏����ɂ��i�K�I, 1�����I�ړ��̗�ł���B�|���̏ꍇ,�I�I�x��,�U�V�L�̔r�������܂Ƃ߂Ă���`���m�}��|���Ƃ��������ł�,���s�ɕ��ԃI�I�x��,�U�V�L�̂���,�I�I�x������,�U�V�L����ɂ���ׂ��Ƃ���Ă�����, ���ꂪ�t�ł����Ȃ����R�͂Ȃ��͂��ł���B�܂��q���Ƃ����ϓ_���猾���Ίe�������ɑ|���o���������悢�͂��ł���,�֏�,���C���Q���J����,�R�G�j���E���Q���J���������Ɍ��������ɂ���̂��s���ł���B������Ԃł����l��,���ǂ����앨���Ȃ��Q�������Ȃ�1���ɍs���邱�ƂƋ���,�J�~����V���ɔr������O�ɂ킴�킴��{�Ƃ��o�R��, ������TS����J�~�Ɍ�����NN�̑O��ʂ�Ƃ����o�H���Ƃ邱�Ƃ������ł��Ȃ��B����̃z���h�E����1�����u���Ƃ͌����Ă��i�K��, ���������̒i�K���ߔm�V���ɂ���ĕύX���Ȃ��Ƃ����_�͐����s�\�ł���B
�����������������������͏Z�����,������Ԃւ̉��l�ϓ��e�̂��߂ł���ƍl����Ȃ�,���ɍ����I�ɐ����ł���̂ł���B
�܂��i�K�ł���B�I�I�x��,�U�V�L,�`���m�}�c�c�Ƃ����K�����������I�ɖ��m�ł͂Ȃ��敪��,�l�X�̉��l�ςɂ����鎞�Ԍ����ɂ��ƂÂ����g�V����,�ˎ�,���,�q���Ƃ����敪���ے�����ݒ�ł�������,�r���������̋敪�ɑΉ����Ēi�K�I�ɔr�����ꂽ�B���ɋ敪�Ԃœ���̐쒸���ɂ��r������������Ă�����, ���̏����͎��̓J�~����V���w�Ƃ�������̕����ł���, ���̓�������邱�Ƃ͑��J�~����V���w�Ƃ��������������邱�Ƃ��Ӗ�����B�����Ă��̃J�~, �V���͐l�X�̉��l�ςɂ�����D��L��ʐ����ے��I�Ɏ������ʂł������B�܂�1�����u���̓������l�X�̉��l�ςɂ����錴���ƈ�v����B�V�v�w��2�g�����Ƃ��Ă��g�V�����Ƃ����̂�1�g�����ł���, 2�g�͗D��̊W�ɂ������B���S������,�����̕��Ƃ��}���ꂵ�Ă��Ă�,��{�Ƃ̒��ڂ̕��Ƃ����Ƃɏo�������ɂ��܂�������,����Ɏ}�̓��ł����l��1�����I�ɏ��t������ׂ��Ƃ���Ă����B�����Č��ǍŌ�͑S���ʂ�NN�Ƃ�����{�ƂɎ�������̂ł������B�����Ĕr�����̓����͍L�t���̗t���^��, 2�����̋�ԂɎU���e�Z����1�����I�����W�Ɍ���ł����B�����r�������e�i�K�����̏����ɒ~�ς���,�r������Ă�������,�Ⴆ�I�I�x������U�V�L�w�Ƒ|���Ă������Ƃ�,�I�I�x���ƃU�V�L���A��������Ɠ�����,�D��̕]����,�Œ肷�邱�ƂɂȂ�͂��ł���B�J�~����V���w�z���h�E����i�K���グ�Ȃ��玀�̂��ړ����Ă������Ƃ�,�J�~���̒i�K�̋�Ԃɂ���Z����,�V�����̒i�K�̋�Ԃɂ���Z���Ƃ̊ԂɗD���,�Œ肷��͂��ł���B�����Ă����͕ύX����邱�Ƃ��Ȃ�, �������r�����Ƃ����������ׂ����̂�,����Ƃ����l�X�̒��ڂ𗁂т�@���,�ЂƂ���ڂɓ���₷���悤�ɂ��Đl�X���g�Ɍ�������Ƃ����킯�ł���B�v����ɔr�t���̓�����,���Ƃ����s�ɕ���ł��Ă������܂ŃI�I�x���̕����J�~,���Ȃ킿�g�V�����̕����D�ʂł���, ���͂�J�~�Ɉʒu���Ă��Ȃ��Ă�,�{�Ƃ͂����܂ŃJ�~,���Ȃ킿�D�ʂł��邱�Ɠ���,�Œ肷�邱�ƂɂȂ�B�܂�͐l�X�̉��l�ςł��鎞�Ԍ�����,�l�X�̒�Z�����Ԃł��郀�����,�Z����Ԃւ̓��e�Ƃ��̕,�����̂��߂̓����ł���, �Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
�������Č��ʂɂ����Ĕr�t����,���̓����ɂ����,�܂����T�C�N�����ێ���,�ړ�������������,�ړ����x��ቺ����,�l�X�̖ڂɂƂ܂邱�Ƃɂ���Đl�X�̔r�����ւ̊S���ێ���,�s�������ɘa����Ƃ������Ԋw�I�ɂ��G�ꂽ�����@���ێ�����B����ɉ����Đl�X�ɑ��Ėڗ�������,�|������ē��X�֗^������Ƃ��������Ƃɂ�鋳��I�ȋ@�\�������p����,���l�ς̓��e,�,���Ȃ킿��Ԃ�������,����ɂ͉��l�ς��ێ����Ă������Ƃ����\�ɂ���Ƃ���,����Ώے��I�@�\��]������,�L���ɗ��p����Ă���, �Ƃ����킯�ł���B
�i�R�j
����������������Ă����,�s�s�ɂ�����r������s�s��Ԃ̕s�����Ƃ��������ɑ��钼�ړI�Ή��������Œ����ɒ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ɂ��Ă�,�t���ʂɂ��Ȃ蓾��Z�p�I�Ή��Ƃ͂܂������قȂ��������l�ފw�E�Љ�S���w�I���_����̌������ɂ߂ėL�����d�v�ł���,��̓I���ʂ������邱�Ƃ��ł���͂��ł���, �ƍl����̂ł���B
��
1)�n������ 1985,�u�]���̒f�ł��锽��, �S�~�푈�v�w�����ł����Ǝj�x �ʍ���46�vJicc�o�ŋ�
2)�C�U�x���E�o�[�h �w���n���{�I�s�x �������g�� 1973,���}��
�W�����E���f�B�E�u���b�N �w�����O�E�W���p���x �˂��܂���,���r���q�� 1970,���}�ЃG�h���[�h�ES �E���[�X�w���{���̓����̓�1�x�ΐ�ӈ�� 1970,���}��
3)��Y�o 1982,�w��������݂��s�s�@�����j�I�Ɂx���{�����o�ŋ���
4)��Y�o 1976,�u�����v ��Y�o,���搳�j, �ĎR�r���� �w�����w���Ƃ͂��� ���{�����̌����x�u�k��
5)�~�����v,�����G�r,��������,�ĎR�r���C���X�؍��� 1972,�w���{�l�̂����� ���������w�w�̎��݁x�����V����
6)���܂��� 1979�C3�C9 �����V��
7)���q����1979,�����L�� �w�w�Z�|���|���̐l�Ԍ`���I�����x �w���o��
8)���c���j 1979,�u�ؖȈȑO�̎��v �w��{���c���j�W�x��g���X
�哇���F,��ޗ��ԕ� 1984,�w�|���̖����w�x�O��䏑�X
9)�ĎR�r�� 1986,�w�s�s�ƍՂ�̐l�ފw�x �͏o���[�V��
10)������1966,�w�]�˂ƍ]�ˏ�x�����o�ʼn�
11)���zᩔV 1986,�u�����r���̂䂭���v ���zᩔV, �Óc�R�I�q�ҁw���Ɛl�̊��j ���i�Ε��x�䒃�̐����[
12)�����D��@1982,�w�]�˂̖��̓��x�g��O����